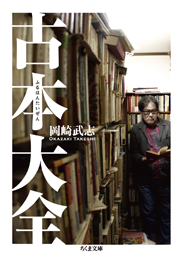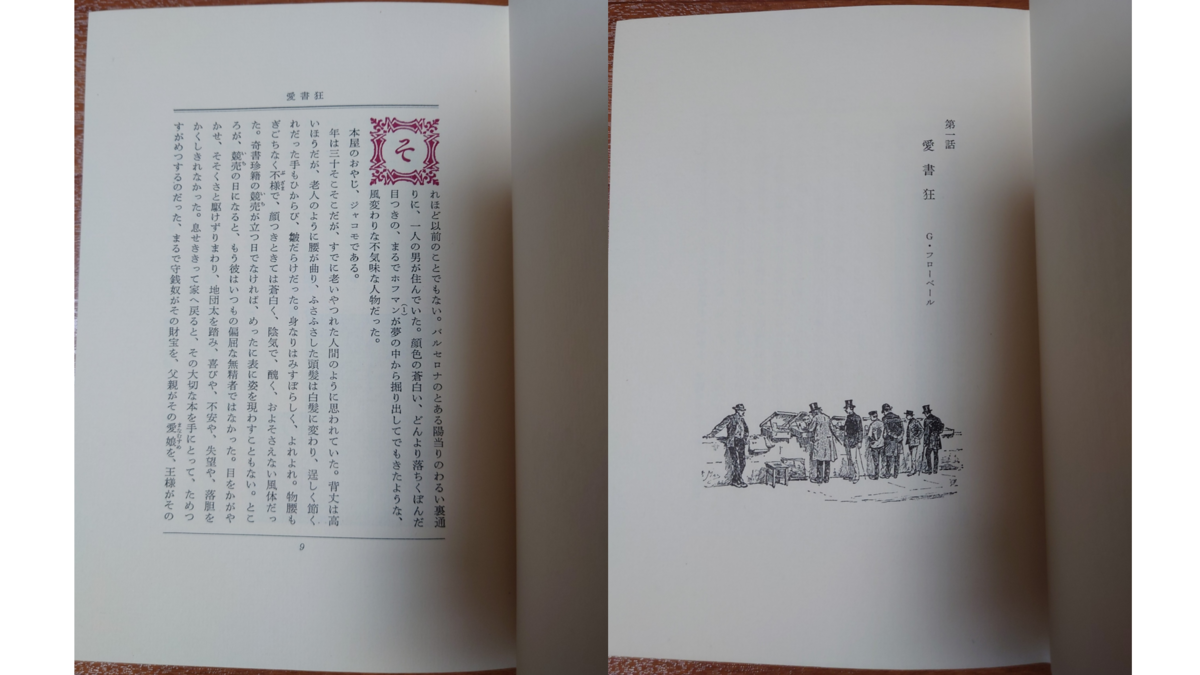先日、日本近代文学館へ行ってきた。ちょうど新収蔵資料展というのをやっていた。新収蔵資料展 - 日本近代文学館 (bungakukan.or.jp)
昨年の新収蔵資料のうちからの展示で、色々と興味深いものがあった。坂上弘の原稿、長田弘の「世界は一冊の本」の原稿や、福永武彦の書簡など(「玩草亭百花譜」や「病牀日録」の原本も展示されていたが、後半では展示替えになってしまった)。大江健三郎の「性的人間」の原稿も出ており、内容に比して独特の文字であり、何とも言えない気持ちにさせられた(「何とも」の中身については今回は明言を避けるが…)。
そのなかで中村真一郎の「新長篇小説の構想」メモというのが展示されていたので、全文書き写してきました。
中村真一郎「新長篇小説の構想」メモ
「90年代仕事計劃 緑川氏に呈出」と書かれた封筒に収められていた。緑川氏は当時の岩波書店社長緑川亨(1923-2009)。「四季」四部作以降の長篇小説の構想がつづられ、「老主人公が性的快楽の未知の残された冒険に没頭」など具体的なイメージがみられる。
岩波書店寄贈
新長篇小説の構想
意図 前作「四季」四部作において完成した「東西西洋のの人文主義」と「宇宙の一者との集合」の人間観を、根底からもう一度、人類の集合的無意識にまで沈下して分解し、主人公に人間の可能性の全領域を経験させる。
着想 死を眺めた老主人公が性的快楽の未知の残された冒険に没頭
構想 そのためのドストイエフスキー的深淵と、サッカレー的ロマネスクの展開の組み合わせ
地肌 可能なかぎり、精密な感覚的描写と形而上学的考察との対位法的表現
主題 性や貧富や年齢による人間の崇高さと愚劣さの全てのオクターヴの表現、特に女性の貞節さときまぐれの二面性の秘密
筋 両性の欲望を持つ引退した老実業家と若い美容師の男性と人気女優との共同生活への過程と、その美容師の客である娘の献身的貞節
効果 最も猥褻な貞操小説「クレーヴの奥方」の裏返し
手法 フォークナー式の形式のなかに、生者死者の人物たちの「意識の流れ」の導入、時間からの解放、あの世への出入
人物 女性たちの男性との根本的相違
四重奏がおそらくこのメモにあたるのか。だとしても実際には中央公論社から出ることになってしまったのでそのあたりの経緯は何かあったのであろうか。私は四重奏はまだ未読で、これを機に少しずつ読み始めてみたのだが、確かに上記メモを窺わせる男女と“会長”が出てきている。
ご興味ある方は3月30日(土)までに行ってみてはいかがでしょうか。